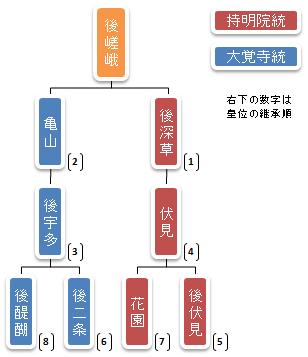木曽義仲の法住寺殿焼き打ち
寿永2年(1183年)7月に平家が都を落ち、代わりに入京したのが木曽義仲とその叔父の源行家でした。 この時、一番喜んだのはおそらく後白河法皇だったのではないでしょうか。 なぜなら、平家は都を落ちて西国に向かうことを決定した際、後白河法皇を都から連れ出そうとしていたからです。 その計画を知った法皇は、平家の探索から逃れるためにどこかへと姿をくらまし、息を殺して危険が過ぎ去るのを待っていました。 平家が都を去り難を逃れた法皇でしたが、実はこの後、更なる問題に直面することとなります。