
アジサイとボダイジュが咲く金戒光明寺に参拝・2022年
6月中旬に要法寺にカモの親子を見に行った後、北東に約15分歩き金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に参拝しました。 6月の金戒光明寺では、境内の所々でアジサイが咲きます。 また、阿弥陀堂の前に植えられているボダイジュも小さな黄色い花を咲かせますね。

6月中旬に要法寺にカモの親子を見に行った後、北東に約15分歩き金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に参拝しました。 6月の金戒光明寺では、境内の所々でアジサイが咲きます。 また、阿弥陀堂の前に植えられているボダイジュも小さな黄色い花を咲かせますね。

6月中旬。 京都市左京区の要法寺(ようぼうじ)に参拝しました。 要法寺では、毎年4月にカモの雛が誕生し、6月頃に鴨川に引っ越しをします。 今年も、そろそろ引越しの時期になったのですが、まだニュースになっていません。 もしかすると、カモは要法寺の清涼池にいるのではないかと思い、当寺を訪れた次第です。

京都市内の東を流れる鴨川は、そのほとりを地元の人が散歩やジョギングをしたり、旅行者や観光客が京都の景色を楽しむために歩いたりしています。 鴨川は、京阪電車の出町柳駅付近で、東の高野川と西の賀茂川が合流して鴨川となります。 賀茂大橋の中央に立ち、北を望むときれいな「Y」の形に賀茂川と高野川が合流しているのがわかりますね。 その鴨川ですが、かつては、今よりも西の堀川の辺りを流れていたという説があります。

京都市上京区にある京都御所は、月曜日と特定の日を除き、通年で公開されています。 誰でも、京都御所に行けば無料で拝観できるのがありがたいですね。 京都御所は、敷地が広いので見ごたえがありますが、京都御所だけを拝観して帰るのはもったいないです。 周辺には、興味深い神社やお寺があるので、京都御所の拝観後に立ち寄っておきたいです。 ということで、今回は、京都御所の拝観後に訪れたい周辺の神社とお寺を紹介します。

京都市北区の船岡山の西に千本通があります。 千本通の名の由来は、卒塔婆が千本立てられたからだと伝えられています。 この地は、蓮台野と呼ばれ、平安時代には風葬が行われていたことから、卒塔婆がたくさん立てられていたのでしょう。 そして、千本通には、蓮台野墓地の墓守の寺として創建された上品蓮台寺(じょうぼんれんだいじ)が今もあります。 また、上品蓮台寺の南には引接寺(いんじょうじ)というお寺も建ち、上品蓮台寺と深い関係があります。

京都に平安京が造営されたのは、この地が四神相応の地だったことが理由として挙げられます。 四神とは、東を守る青龍、西を守る白虎、南を守る朱雀、北を守る玄武の神さまのことです。 そして、四神相応の地とは、東に川、西に道、南に湖、北に山がある土地を指し、これを京都に当てはめると東に鴨川、西に山陰道、南に巨椋池(おぐらいけ)、北に船岡山となります。 これら四神の中で、平安京造営の起点となったのは船岡山と考えられます。
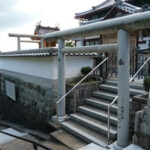
京都市東山区の維新の道を登っていくと、京都霊山護国神社(きょうとりょうぜんごこくじんじゃ)が建っています。 そこから南に少し歩くと、細い石段が山に向かって延びています。 石段を上った先には正法寺というお寺があるのですが、その途中には個人のお宅のような神社があります。 その神社は、霊明神社といいます。

京都市東山区の清水寺を拝観し、境内を巡って出口に近づこうかというところに2つの茶屋があります。 1軒は舌切茶屋、もう1軒は忠僕茶屋といいます。 春と秋の行楽シーズンでは、どちらの茶屋も人が多く大変賑わっていますね。 今は、観光客が、歓談しながら、お茶を飲んだり食事をしたりしている舌切茶屋と忠僕茶屋ですが、2つの茶屋が清水寺で営業を始めたのは、幕末の安政の大獄と関係しています。

京都府乙訓郡大山崎町の天王山のふもとに室町時代の連歌師であった山崎宗鑑の冷泉庵跡を示す石碑が置かれています。 滋賀県栗太郡常盤村志那で生まれた山崎宗鑑は、室町幕府9代将軍の足利義尚に仕えていましたが、義尚が近江で戦没した際、世の無常を感じて出家し大山崎に隠棲しました。 ちなみに出家する前は、志那弥三郎範重と名乗っていました。

京都府乙訓郡大山崎町のJR山崎駅を出てすぐのところにフェンスで囲まれた土地があります。 どこかの会社が取得し、これからビルでも建てるのかなと思えるような土地なのですが、近くに説明書が設置されており、「山崎駅跡・河陽離宮(かやりきゅう)跡と離宮八幡宮の池跡」と記されていました。 JR山崎駅のかつての駅舎があった場所かと思ってしまいますが、そうではありません。