
暑い夏でも涼しい気持ちにしてくれる梅小路公園
京都の中心部は、近代的な建物が多いのですが、お寺や神社の境内に入ってみると、視界からそのような建物が消えて、数百年前の時代にさかのぼったように感じたり、自然の中に入り込んだように感じることがよくあります。 京都駅から西に15分ほど歩いた辺りにある梅小路公園も、そのように感じる場所のひとつです。
観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

京都の中心部は、近代的な建物が多いのですが、お寺や神社の境内に入ってみると、視界からそのような建物が消えて、数百年前の時代にさかのぼったように感じたり、自然の中に入り込んだように感じることがよくあります。 京都駅から西に15分ほど歩いた辺りにある梅小路公園も、そのように感じる場所のひとつです。

驕る平家は久しからず。 寿永2年(1183年)7月、かつて栄華を極めた平家が、都から落ちていくことになりました。

幕末の京都では、天誅と称したテロ行為が頻繁に起こっていました。 その多くが、尊王(天皇を敬うこと)や攘夷(じょうい=外国人を追い出すこと)を主張し、反対派を襲撃するというものでした。 このようなテロ行為の中で、大事件でありながら、歴史上はあまり知られていない事件が文久3年(1863年)8月17日に起こります。 その事件の名は、後に本圀寺事件とか因幡二十士事件と呼ばれるようになります。

京都市下京区の四条烏丸は、京都のビジネス街として有名な地域です。 そのため四条烏丸は、銀行、ホテル、デパート、カフェ、居酒屋など近代的な建物が密集しています。 なので、観光で四条烏丸に訪れる方は多くはありません。 しかし、四条烏丸は、少し路地に入ると意外に多くの神社やお寺が建っています。 そこで、今回は、四条烏丸にある7つの寺社について紹介したいと思います。

西本願寺には、通常非公開の国宝に指定されている飛雲閣という建物があります。 その飛雲閣が4月15日まで一般公開されることになりました。 時間は午後12時くらいから午後3時くらいまで。人数が多い時には入場整理が行われます。 飛雲閣は、普段、めったに見ることができないので、この機会に見ておきたいですね。 と言うことで、4月10日に飛雲閣を拝観してきました。

新撰組が京都に登場したのは、文久3年(1863年)です。 その翌年には、新撰組を有名にした池田屋事件や蛤御門の変が起こっています。 当時の新撰組は、壬生の八木邸を屯所としていましたが、やがて隊士が増えてくると手狭になったため、もっと広い場所に屯所を移転する必要が出てきました。 そこで、慶応元年(1865年)3月10日に第2の屯所に移転することになります。 その第2の屯所が、現在、世界遺産に登録されている西本願寺だったのです。

京阪電車の清水五条駅で降りる観光客の方の多くが、清水寺へ行くために東に歩いて行きます。 また、清水五条駅から15分ほど西に歩いた場所に地下鉄五条駅があるのですが、こちらで降りる方は、その周辺で働いていることが多く、観光目的の方が少ないですね。 そのため、清水五条駅から地下鉄五条駅までの一帯は、あまり観光客の方が訪れません。 でも、両駅の中間あたりにある富小路通には、本覚寺、上徳寺、蓮光寺、長講堂といった興味深いお寺が建っています。 そこで、今回は、これらのお寺について紹介したいと思います。

阪急電車の京都の終点である河原町駅には、阪急百貨店が建っています。 河原町と言えば、阪急百貨店と高島屋がシンボルのような存在ですが、そのひとつの阪急百貨店が2010年秋に閉店することになりました。
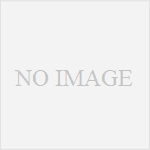
旅行で京都に訪れる際に必要となるのが宿の確保ですよね。 日帰り観光の場合は宿泊する必要はありませんが、1泊2日や2泊3日といった日程で京都にお越しになる場合には、どうしても宿に泊まらなければなりません。 京都の観光名所は、拝観料を納めないと入れないところが多いので、宿泊代はできるだけ安く抑えておきたいところです。 また、泊まる場所もできるだけ京都駅に近い方が観光には便利です。 そこで、今回は京都駅近くのホテルにできるだけ安く泊まるには、どういう選択をした方がいいかを紹介したいと思います。

銀行や証券会社など金融機関が多く軒を並べている京都市下京区の四条烏丸。 四条烏丸は、京都のビジネス街として有名な地域なので、近代的なビルがたくさん建っています。 烏丸通と四条通が交差するあたりは、交通量が多く、道路はバスや自動車であふれており、また歩道はビジネスマンの方やショッピングをされている方で賑わっています。 そんな近代的なビジネス街や繁華街のある四条烏丸ですが、大きな通りから小さな路地に入ると意外とたくさんの神社やお寺が残っています。 今回紹介する平等寺は、地下鉄四条駅から南に少し歩いたあたりに建っているお寺で、変わった伝説が残っています。