
出水の枝垂れ桜も近衛邸跡の糸桜も満開・京都御苑
まだ肌寒さが残る3月下旬。 お花見には、まだ早いだろうと思うでしょうが、実はもう桜が満開になっているところがあります。 それはどこかというと、京都市上京区の京都御苑です。 京都御苑には、早咲きの桜が植えられており、ソメイヨシノが開花する頃、いやそれよりも早く見ごろを迎えます。 ということで、3月22日に京都御苑を訪れました。

まだ肌寒さが残る3月下旬。 お花見には、まだ早いだろうと思うでしょうが、実はもう桜が満開になっているところがあります。 それはどこかというと、京都市上京区の京都御苑です。 京都御苑には、早咲きの桜が植えられており、ソメイヨシノが開花する頃、いやそれよりも早く見ごろを迎えます。 ということで、3月22日に京都御苑を訪れました。

3月下旬になると、そろそろ梅が終わりに近づき、主役が桜に代わる頃ですね。 2013年は、梅の開花が遅く、2月はどこに行っても空振りといった感じでした。 でも、3月に入ると、急に暖かくなって、梅の開花が一気に進み、どこも一斉に見ごろを迎えました。 今回の記事は、2013年に訪れた梅の名所のまとめです。

いよいよお花見シーズン。 京都には、たくさんの桜の名所がありますので、基本的にどこに行ってもお花見することができます。 でも、どうせ桜を見るなら事前に下調べをしておいた方が、何かと都合が良いですよね。 特に見ごろ時期やどれくらいの桜があるのかを事前に知っていた方が、現地に到着した時に期待とは違ったといったことが少なくて済みます。 ということで、今まで訪れたことがある桜の名所の写真をイメージギャラリーにして公開し、いつごろ見ごろになるのかなどの情報を掲載することにしました。
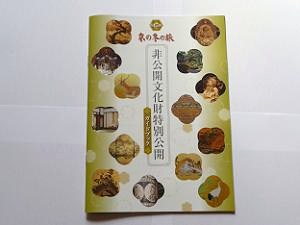
毎年冬になると京都市観光協会が主催する「京の冬の旅」と題した非公開文化財特別公開が行われます。 2013年は、1月10日から3月18日まで行われました。 普段、見ることができない文化財を鑑賞することができる貴重な機会なので、私も訪れたのですが、残念ながら今年は3ヶ所だけしか拝観することができませんでした。

京都市伏見区にある京都競馬場の裏に淀水路があります。 この淀水路沿いの遊歩道には、多くの河津桜が植えられており、本格的なお花見シーズンよりも早い3月中旬から下旬にかけて見頃を迎えます。 3月17日。 そろそろ良い具合に河津桜が咲いているだろうと思い、淀水路を訪れました。

京都御苑の西に建つ菅原院天満宮神社は、最近、境内がすっきりとした感じになっています。 以前は、何かごちゃごちゃとしているような雰囲気で、それが逆に境内に何があるのかわからない印象を与えていたように思えます。 ということで、今回の記事では、すっきりとした菅原院天満宮神社の境内の様子をお伝えします。

京都府八幡市に足立寺史跡公園(そくりゅうじしせきこうえん)という公園があります。 地元の人にしか知られていませんが、この公園は梅の名所であります。 もしかしたら、地元の人でも、知らない人の方が多いかもしれません。 私が足立寺史跡公園に訪れたのは、3月中旬でした。

3月中旬。 京都御苑の梅林に行ってきました。 今年はこれで3回目ですね。 過去2回は、梅の咲き具合がもうひとつでしたが、さすがに3月中旬ともなると、多くの梅が花を咲かせていることでしょう。 また、この日は、京都御苑の南東に建つ下御霊神社(しもごりょうじんじゃ)にも訪れました。

毎年、冬になると京都市観光協会が催す「京の冬の旅」。 この企画では、普段目にすることができない非公開文化財を鑑賞することができます。 2013年は、ガイドブックを200円で購入し、どこに行こうかといろいろと眺めて、絶対に拝観しようと思ったところがありました。 そこは、京都市左京区の霊鑑寺です。 霊鑑寺は、椿の寺として名高いことから、見ごろを迎えるであろう3月中旬まで待って、拝観してきました。

3月に入って京都も暖かい日が続き、各地で一気に梅が見ごろを迎え始めました。 2013年の梅は、例年よりも開花が遅かったのですが、ようやく観梅が楽しめるようになりました。 3月11日。 京都市左京区の下鴨神社に梅を見に行ってきました。