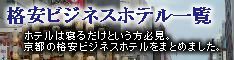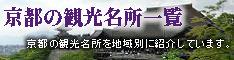東寺を紹介しています。
由緒、見どころ、所在地、最寄駅などの情報を掲載。
東寺

由緒
東寺は、平安遷都(794年)の際に羅城門の東西に王城鎮護を目的として建てられた東側の官寺で、延暦15年(796年)に建立された。山号は八幡山。東寺真言宗総本山。
羅城門の西側には西寺が建立されたが現存していない。
その後、弘仁14年(823年)に嵯峨天皇から空海に下賜され、真言密教の根本道場となった。この時に金光明四天王教王護国寺秘密伝法院と改称されたが、教王護国寺または東寺と呼ばれることが多い。
天長2年(825年)に講堂の造営が行われ、翌年には五重塔の造営が行われている。また、同5年には、綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)も建立された。
しかし、承和2年(835年)に空海が高野山に入定して以後に衰退が始まる。また、天喜3年(1055年)には五重塔が落雷で焼失している。
東寺の再建が行われたのは平安時代末期のことで、後白河法皇と関係の深かった文覚(もんがく)が東寺修造の財源として播磨一国を知行国とした。また、源頼朝も後白河法皇の追善供養として修造に寄与している。
だが、頼朝が亡くなり、文覚も失脚したことで再建は中断される。
その後は、後白河法皇の皇女・宣陽門院が荘園の寄進を行ったことなどで東寺は維持され、天福元年(1233年)には仏師の康勝が大師堂に弘法大師像を安置した。
また、正和2年(1313年)に後宇多天皇も多くの荘園を寄進している。
建武3年(1336年)には足利尊氏が東寺に本陣を置き、室町時代に伽藍は充実したが、文明18年(1486年)の土一揆によって五重塔や大師堂は残ったものの多くの伽藍が焼失した。
その後、織田信長が入京した際に東寺を宿所としたことから再建を支援した。また、豊臣秀吉や徳川家康も再建に尽力している。
文禄5年(1596年)に大地震により講堂などが大破したが、慶長4年(1599年)に豊臣家が金堂の再建に着手し同10年に完成した。また、この頃に秀吉の妻・北政所(きたのまんどころ)が講堂を修復している。
寛永12年(1635年)に五重塔が焼失したが、同18年に徳川家光の寄進で再建が始まり、正保元年(1644年)に完成した。
なお、東寺は平成6年(1994年)に世界文化遺産に登録されている。
都七福神
東寺は都七福神のひとつに数えられる。その他は、松ヶ崎大黒天、恵美須神社、六波羅蜜寺、赤山禅院、万福寺、行願寺である。
ご利益
学業成就、交通安全、諸願成就
慶賀門

東寺の東側にある慶賀門。南の南大門だけでなくこちらの門からも入ることができる。
宝蔵

東寺の創建当時に近い年代に建立されたとされる。現在の宝蔵は、建久9年(1198年)に文覚によって再建されたものと伝えられている。
食堂

僧侶が斎時に集まって食事をした食堂(じきどう)。食堂内には、様々な像が安置されているが、火災によって腕などが損傷している。
夜叉神堂

当初は南大門の左右に安置されていた夜叉神像を安置している。しかし、拝まずに通った旅人に罰があたったとされたことから中門の左右に移された。慶長元年に中門が倒壊した後、現在の夜叉神堂に安置した。
八重紅枝垂れ桜

岩手県盛岡市で育てられた桜。平成6年に秋田県を経て三重県鈴鹿市に移り、同18年に弘法大師入唐求法の旅からの帰朝1200年を記念して東寺に寄贈された。
講堂

延徳3年(1491年)に再建された講堂。重要文化財の大日如来や国宝の梵天、帝釈天、不動明王などが安置されている。
金堂

慶長10年に再建された金堂。重要文化財の薬師如来坐像、日光菩薩像、月光菩薩像などが安置されている。
五重塔

寛永21年に再建された五重塔。高さ約55メートルで現存する国内の古塔で最も高い。内部には心中を囲む四仏坐像が安置されている。
毘沙門堂

平将門の乱(939年)の際に都の守護神として祀った兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)を安置していた毘沙門堂。当初は羅城門に安置されていたが、移転を繰り返し文政5年(1822年)に毘沙門堂を建立して祀った。現在、兜跋毘沙門天は宝物館に安置されている。
天降石

毘沙門堂の近くにある天降石(てんこうせき)。石を撫でた手で体の悪い部位を擦ると治ると言われている。
大師堂

西院御影堂とも呼ばれる大師堂。国宝の大師像や不動明王像が安置されている。
大日堂

元禄11年(1698年)に大師堂の礼拝堂として建立された大日堂。
東寺の所在地
〒601-8473
京都市南区九条町1(地図)
東寺への行き方
近鉄東寺駅から徒歩約5分
※講堂、金堂、五重塔の敷地内へは拝観料500円から800円が必要。五重塔初層特別公開は800円から1,200円。
東寺周辺の宿泊施設
スポンサード リンク
関連記事
- 東寺の春夏秋冬
- 東寺の五重塔の心柱の役割
- 晴天の下で見る東寺のハス・2024年
- 冬の曇り空の日に参拝した東寺・2024年
- 東寺で咲くハス・2023年
- 秋晴れの日に東寺の境内を歩く・2022年
- 初夏から梅雨こそ京都の有名な観光名所を訪れたい
- 弘法市で賑わう早春の東寺・2022年
- 東寺に参拝したら必ず見ておきたい建物
- 東寺の濠で咲くハス・2021年
- 梅雨の東寺に参拝・2021年
- ハスが咲く東寺に参拝・2020年
- 秋雨降る東寺に参拝・2019年
- 東寺で見ごろを迎えた桜・2019年
- 東寺で見ごろを迎えた紅葉・2018年
- 春にはまだ早い東寺の境内・2018年
- 秋の気配が漂い始めた東寺・2017年
- 東寺の紅葉ライトアップ・2016年
- 東寺の万病ぬぐいの贔屓
- 東寺の夜桜ライトアップで金色に輝く五重塔・2016年
- 京都の紅葉狩りコース-東寺、西本願寺編
- 秋の東寺参拝・2015年
- 日本最初の私立学校を開校したのは東寺の空海
- 京都の桜散策コース-東寺、六孫王神社、梅小路公園、渉成園編
- 東寺は桜か紅葉見るならとっぢ?
- 東寺の東大門が不開門と呼ばれている理由
- 大友貞載と刺し違えた南朝の忠臣結城親光
- 東寺の拝観エリアの外の紅葉
- 瓢箪池の周囲を真っ赤に染める紅葉・東寺
- 後醍醐天皇の還幸を待ち望んだ東寺の見返りの松
- わずか数十騎で楠木正成討伐に向かった宇都宮公綱
- 東寺と教王護国寺はどちらが正式名称なのか?
- 東寺の夏の風景・2013年
- 東寺の瓢箪池はなぜ造られたのか?
- 異例の早さで満開となった不二桜・東寺
- 桜と一緒に撮影できる五重塔
- 東寺の毘沙門天と三面大黒天と鎮守八幡宮にお参り
- 京の三弘法めぐり
- 河津桜と梅が咲く風景・東寺
- 弘法市と天神市
- 京都駅からすぐ。東寺と東本願寺のハス
- 五重塔で有名な東寺を拝観
- 五重塔以外にも観るものがたくさんある東寺
- 東寺があるのに西寺がない理由
| 付近の主な観光名所 | ||
 観智院 |
 東福寺 |
 西本願寺 |
 泉涌寺 |
 渉成園 |
 東本願寺 |