
平安京の西市の跡地にある平安京野寺小路跡の石碑
平安京には、東市(ひがしのいち)と西市(にしのいち)という2つの市場がありました。 人が多く住む場所には、市場は欠かすことができませんから、平安京でも東西の市が設けられていたんですね。 市場のうち西市の西側には野寺小路(のでらこうじ)という小路が面しており、現在その場所には平安京野寺小路跡を示す石碑が立っています。
観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

平安京には、東市(ひがしのいち)と西市(にしのいち)という2つの市場がありました。 人が多く住む場所には、市場は欠かすことができませんから、平安京でも東西の市が設けられていたんですね。 市場のうち西市の西側には野寺小路(のでらこうじ)という小路が面しており、現在その場所には平安京野寺小路跡を示す石碑が立っています。

京都市の中心部を北から南に流れる堀川。 堀川には、西堀川と東堀川の2つがあり、現在の堀川は東堀川を指します。 では、西堀川はどうなったのかというと、紙屋川という名で呼ばれています。 その紙屋川の清流は、平安時代に紙すきのために利用され、紙屋院という製紙工場も造られていました。

承久3年(1221年)5月14日。 後鳥羽上皇が、鎌倉幕府を倒すために挙兵した承久の乱が起こりました。 上皇が、乱を起こす決意をしたのは、現在の京都市伏見区の鳥羽にある城南宮です。
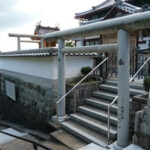
京都市東山区の維新の道を登っていくと、京都霊山護国神社(きょうとりょうぜんごこくじんじゃ)が建っています。 そこから南に少し歩くと、細い石段が山に向かって延びています。 石段を上った先には正法寺というお寺があるのですが、その途中には個人のお宅のような神社があります。 その神社は、霊明神社といいます。

京都府乙訓郡大山崎町の天王山のふもとに室町時代の連歌師であった山崎宗鑑の冷泉庵跡を示す石碑が置かれています。 滋賀県栗太郡常盤村志那で生まれた山崎宗鑑は、室町幕府9代将軍の足利義尚に仕えていましたが、義尚が近江で戦没した際、世の無常を感じて出家し大山崎に隠棲しました。 ちなみに出家する前は、志那弥三郎範重と名乗っていました。

京都府乙訓郡大山崎町のJR山崎駅を出てすぐのところにフェンスで囲まれた土地があります。 どこかの会社が取得し、これからビルでも建てるのかなと思えるような土地なのですが、近くに説明書が設置されており、「山崎駅跡・河陽離宮(かやりきゅう)跡と離宮八幡宮の池跡」と記されていました。 JR山崎駅のかつての駅舎があった場所かと思ってしまいますが、そうではありません。

先日、離宮八幡宮に参拝した時、境内の隅に置かれた塔心礎を見ました。 塔心礎は、五重塔など木造塔の中央に立つ心柱を支える礎石のことです。 五重塔と言えば、東寺や醍醐寺など京都市内に4つありますが、離宮八幡宮が建つ大山崎町にも、五重塔のような木造塔があったんですね。

平安時代に疫病の流行や自然災害が起こると、高貴な人の怨霊の仕業だと考えられていました。 当時の人々は、疫病や自然災害から身を守るためには、恨みを持って非業の死を遂げた人々の怨霊を鎮めれば良いと考え、祭をしたり、神社に祀ったりしました。 これを御霊信仰(ごりょうしんこう)といいます。 京都で夏に行われる祇園祭は、貞観5年(863年)に神泉苑で行われた御霊会(ごりょうえ)が起源ですし、今も京都には非業の死を遂げた人々を祀っている神社が残っています。 今回は、御霊信仰を今も伝えている京都の神社を紹介します。

永禄11年(1568年)9月に上洛し、当時の政治に深く関わった織田信長。 今でも、京都には、織田信長に関係する史跡が残っています。 そこで、今回は、京都にある織田信長に関係する史跡をいくつか紹介します。

叡山電車の木野駅を出て南に約3分歩いたところに妙満寺という日蓮宗のお寺があります。 かつては、中京区にあった妙満寺は、昭和43年(1968年)に閑静な現在地に移転しています。 その妙満寺には、雪月花の三名園のうちの雪の庭があります。 雪の庭は拝観することができ、その際、安珍と清姫の鐘と呼ばれる道成寺(どうじょうじ)の鐘も鑑賞できます。