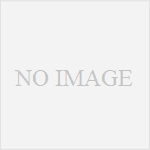京都駅近くに建つ便利な合格祈願の社・文子天満宮
1月と言えば、受験生にとっては最後の追い込みで忙しい時期ですよね。 親御さんにしてみても、わが子が合格するようにと祈りたくなることでしょう。 京都で合格祈願と言えば、学問の神さまの菅原道真を祀っている北野天満宮が有名です。 ただ、北野天満宮は、京都駅から市バスに乗って30分程度かかるため、参拝するのが若干不便です。 菅原道真に合格祈願したいけど、北野天満宮まで行く時間がないという方におすすめなのが、京都駅から北に10分ほど歩いた辺りに建っている文子天満宮(あやこてんまんぐう)です。