
アジサイとボダイジュが咲く金戒光明寺に参拝・2022年
6月中旬に要法寺にカモの親子を見に行った後、北東に約15分歩き金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に参拝しました。 6月の金戒光明寺では、境内の所々でアジサイが咲きます。 また、阿弥陀堂の前に植えられているボダイジュも小さな黄色い花を咲かせますね。
観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

6月中旬に要法寺にカモの親子を見に行った後、北東に約15分歩き金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に参拝しました。 6月の金戒光明寺では、境内の所々でアジサイが咲きます。 また、阿弥陀堂の前に植えられているボダイジュも小さな黄色い花を咲かせますね。

5月下旬に京都府乙訓郡大山崎町の宝積寺に参拝した後、山崎聖天の通称で親しまれている観音寺を訪れました。 観音寺に参拝するのも久々で、天王山の中腹に境内があったなということしか覚えていない状況でした。 そのため、新鮮な気持ちで観音寺に向かうことができました。

5月下旬に京都府乙訓郡大山崎町の大念寺に参拝した後、さらに天王山を5分ほど登り、宝積寺(ほうしゃくじ)を訪れました。 宝積寺は、宝寺とも呼ばれています。 宝寺なんて、福を招いてくれそうな縁起の良い名ですね。 天王山を上った時は、宝積寺で、しっかりと福を授かって帰りたいです。

5月下旬に京都府乙訓郡大山崎町の離宮八幡宮に参拝した後、大念寺を訪れました。 大念寺に参拝するのも久しぶりで、どのようなお寺だったか、ほとんど記憶がありません。 小さなお寺だったことは覚えているのですが。

5月下旬。 京都府乙訓郡大山崎町にある離宮八幡宮(りきゅうはちまんぐう)に参拝しました。 以前に離宮八幡宮を訪れたのは10年以上前のことです。 久しぶりだと道に迷いそうになりましたが、なんとかたどり着くことができました。

古くから京都の中心と言われているのが、中京区の六角堂境内にあるへそ石です。 このへそ石は、かつては、六角堂の南側を通る六角通の真ん中にあったのですが、明治10年(1877年)に六角堂境内に移されているので、京都の中心よりやや北にずれています。 桓武天皇が都を平安京に遷した際、道路整備中に六角堂が道路の中央にあたったため、天皇が少しずれてくれるよう祈願したところ、自ら北に移動し、その時に礎石をもとの位置に残していったと伝えられています。 それが、六角堂のへそ石だと。 この説以外にも、へそ石は、水位計の台を支えていた礎石だとする説もあります。

5月中旬。 京都府八幡市の石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)に参拝しました。 石清水八幡宮では、5月になると神苑でサツキが咲き始めます。 満開になると、木々の緑に混ざってピンク色や赤色の花が咲き、初夏らしい光景を見せてくれますね。
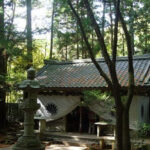
京都の北、左京区にそびえる鞍馬山。 その鞍馬山には、鞍馬寺があります。 鞍馬山も鞍馬寺もパワースポットして人気があり、奥の院魔王殿には、650万年前に金星から降臨したと言い伝えられている魔王が祀られています。

5月中旬に京都市伏見区の与杼神社に参拝した後、南に約3分歩き淀水路を訪れました。 淀水路には、たくさんの河津桜が植えられており、3月になると大勢の観光客が満開になった姿を見にやって来ますが、花が咲いていない時期には、地元の人以外は見かけることはないですね。 満開の河津桜を見に来てから2ヶ月ぶりの淀水路です。

5月中旬。 京都市伏見区の与杼神社(よどじんじゃ)に参拝しました。 与杼神社には、4月に桜を見に来て以来になります。 日ごろから参拝者が少なめの神社ですが、ゴールデンウィークが過ぎると、さらに閑散とします。