
駒形稚児が来なかった綾戸國中神社参拝・祇園祭2022年
毎年7月13日の午後2時から、京都市東山区の八坂神社で、久世稚児社参(くぜちごしゃさん)が行われます。 南区上久世綾戸にある綾戸國中神社(あやとくなかじんじゃ)から、駒形稚児(こまがたちご)がお参りに訪れるのが久世稚児社参です。 駒形稚児は、17日の神幸祭と24日の還幸祭で、中御座の神輿を先導しますが、その前の13日に八坂神社に参拝し、神役奉仕の宣状を受けます。
観光名所、史跡、四季折々の風景を写真とともに紹介するブログ。※アフィリエイト広告を利用していますがポップアップ広告は表示されません。

毎年7月13日の午後2時から、京都市東山区の八坂神社で、久世稚児社参(くぜちごしゃさん)が行われます。 南区上久世綾戸にある綾戸國中神社(あやとくなかじんじゃ)から、駒形稚児(こまがたちご)がお参りに訪れるのが久世稚児社参です。 駒形稚児は、17日の神幸祭と24日の還幸祭で、中御座の神輿を先導しますが、その前の13日に八坂神社に参拝し、神役奉仕の宣状を受けます。

7月13日。 京都市東山区の八坂神社で、祇園祭の長刀鉾稚児社参(なぎなたほこちごしゃさん)が行われました。 長刀鉾のお稚児さんは、この日、四条烏丸の町会所から馬に乗り祇園の八坂神社に参拝し、正五位少将(しょうごいしょうしょう)の位を授かります。

7月上旬に京都市東山区の法住寺にハスを見に行った後、智積院(ちしゃくいん)に参拝しました。 智積院は、四季折々の植物を見ることができるお寺で、夏は、キキョウやハスが花を咲かせます。 梅雨が明け、本格的な夏がやって来たので、そろそろキキョウとハスが良い具合に咲いていることでしょう。

7月上旬に京都市東山区の八坂神社に参拝した後、東隣の円山公園を散策しました。 夏の京都は暑いですが、円山公園は風が吹き抜けるので意外と涼しいです。 もちろん、日向を歩くと暑いですが、木陰を歩けば暑さが和らぎます。

7月上旬に京都市東山区の清水寺に参拝した後、八坂神社を訪れました。 7月の八坂神社は、祇園祭の神事が行われることから、普段にも増して多くの旅行者や観光客がお参りに訪れます。 境内の景色も、普段とは違い祇園祭の雰囲気を感じられるようになっていますね。

7月上旬。 京都市東山区の大谷本廟にハスを見に行った後、清水寺を訪れました。 世界遺産に登録されている清水寺は、国内外の観光客や旅行者に大変人気がありますが、ここ2年はコロナの影響で閑散としています。 もうコロナは落ち着いていますが、まだ海外からの旅行者は少ないので、今も清水寺は混雑してないだろうと思いながら、鳥辺野の墓地の坂道を上っていきました。

7月7日。 京都市東山区の八坂神社で、祇園祭の綾傘鉾稚児社参(あやがさほこちごしゃさん)が行われました。 本来の姿での祇園祭の開催は、実に3年ぶりで、すでに7月1日から祇園祭は始まっています。
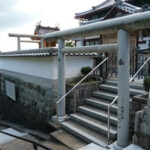
京都市東山区の維新の道を登っていくと、京都霊山護国神社(きょうとりょうぜんごこくじんじゃ)が建っています。 そこから南に少し歩くと、細い石段が山に向かって延びています。 石段を上った先には正法寺というお寺があるのですが、その途中には個人のお宅のような神社があります。 その神社は、霊明神社といいます。

京都市東山区の清水寺を拝観し、境内を巡って出口に近づこうかというところに2つの茶屋があります。 1軒は舌切茶屋、もう1軒は忠僕茶屋といいます。 春と秋の行楽シーズンでは、どちらの茶屋も人が多く大変賑わっていますね。 今は、観光客が、歓談しながら、お茶を飲んだり食事をしたりしている舌切茶屋と忠僕茶屋ですが、2つの茶屋が清水寺で営業を始めたのは、幕末の安政の大獄と関係しています。

ゴールデンウィークが終わると、京都から旅行者や観光客が一気に減ります。 初夏から梅雨にかけての京都は、気候的に散策しやすいので、人が少ないこの時期こそ訪れたいですね。 春や秋の行楽シーズンには、大混雑する観光名所も、初夏や梅雨なら閑散としたものです。 だから、有名な京都の観光名所を訪れるなら、初夏から梅雨がおすすめです。 そこで、今回は、初夏から梅雨に訪れたい京都の有名な観光名所を紹介します。