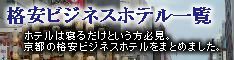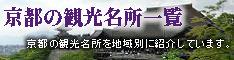伏見稲荷大社を紹介しています。
由緒、見どころ、所在地、最寄駅などの情報を掲載。
伏見稲荷大社

由緒
伏見稲荷大社は、和銅4年(711年)に秦伊呂具(はたのいろく)が稲荷山の山上に社を造り、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、猿田彦命(さるたひこのみこと)、大宮女命(おおみやのめのみこと)を祀ったのが始まりとされる。
祭神は、宇迦之御魂神を主祭神とし、猿田彦命、大宮女命、田中大神(たなかのおおかみ)及び四大神(しのおおかみ)。
伏見稲荷大社は、以前は稲荷大社と称していた。秦伊呂具が餅を的に弓矢に興じていたところ餅が白鳥となり稲荷山の峰に止まり、そこに稲が生えたことが社名の由来と伝えられている。
天長4年(827年)に空海が稲荷神を東寺の鎮守として祀ったとされる。また、仁寿2年(852年)の祈雨奉幣以来、朝廷から度々勅使が遣わされるようになり、天慶5年(942年)には正一位の神階も賜っている。
その後、応仁の乱(1467年)によって本殿が焼失したが、明応8年(1499年)に再建されている。
昭和21年(1946年)に稲荷大社から伏見稲荷大社に改称された。
伏見稲荷大社は、全国に3万社以上あると言われる稲荷神社の総本宮で、五穀豊穣、商売繁盛のご利益があるとして信仰されている。
霊魂社、藤尾社、熊野社

第一鳥居(ページトップの写真)をくぐった左手に建つ霊魂社、藤尾社、熊野社。伏見稲荷大社の境内には、非常に多くの摂社・末社が建っている。
第二鳥居

第一鳥居をしばらく行くと第二鳥居がある。これより先に楼門や本殿が建っている。
楼門

天正17年(1589年)に豊臣秀吉が寄進した楼門。
狐

楼門の左右に鎮座する狐。鳥居と共に伏見稲荷大社の象徴的な建造物。
外拝殿

楼門をくぐってまず最初に目に入るのが外拝殿(げはいでん)。天正17年(1589年)の社頭図には拝殿として描かれており、当時は四間四方の建物であった。天保11年(1840年)に稲荷祭礼の5期の神輿を並べるため、間口五間奥行三間のものに改められた。軒下の吊燈籠は「黄道十二宮」を表している。
この奥に本殿がある。
東丸神社

楼門をくぐって右手には東丸神社(あずままろじんじゃ)が建つ。江戸時代の学者である荷田春満(かだのあずままろ)を祭神とする。学業の神様で合格祈願の受付もしている。創建は明治16年(1883年)。
本殿

五間社流造の本殿。明応8年に再建された後も修復を重ねて現在に至る。
権殿

寛永10年(1635年)に再興された権殿(ごんでん)。明応遷宮記録(1499年)に名が見られることから、この頃に建てられたと考えられる。昭和34年(1959年)に本殿の東北に移築された。
両宮社

天照大皇神と豊受皇大神を祀る両宮社(りょうぐうしゃ)。天正17年の社頭図に「伊勢両宮南向再興」と記されている。元禄7年(1694年)に現在地に社殿を再興。
五社相殿

長禄3年(1459年)の記録に残る若王子社を始め、境内に祀られていた各社を元禄7年に現在地に遷し、五社相殿(ごしゃあいどの)に祀った。
なお、五社は、八幡宮社、日吉社、若王子社、猛尾社、蛭子社である。
荷田社

伏見稲荷大社の旧社家の祖神である荷田氏を祀る荷田社(かだしゃ)。元禄7年に現在地に再興された。
長者社

伏見稲荷大社の旧社家の祖神である秦氏を祀る長者社(ちょうじゃしゃ)。元禄7年以前からある建物を現在地に移したとされる。
神馬舎

本殿の裏手にある神馬舎。神馬は昭和13年に、仔馬は昭和57年に奉納されたもの。
玉山稲荷社

玉山稲荷大神を祀る玉山稲荷社。東山天皇が宮中に奉祀していた稲荷社を崩御の後、松尾月読神社の社家松室重興が預かり、高野の私邸内に遷座した。明治7年(1874年)に諸般の都合で伏見稲荷大社に遷される。社殿は明治8年建立。
白狐社

命婦専女神(みょうぶとうめのかみ)を祀る白狐社(びゃっこしゃ)。稲荷大神の眷属(けんぞく)を祀る唯一の社である。古くは、奥之命婦や命婦社とも呼ばれていた。元禄7年までは現在の玉山稲荷社の近くに祀られていた。
奥宮

本殿と同じ流造の奥宮(おくみや)。摂社でも末社でもなく、稲荷大神を祀ることから他の境内社とは別格とされる。天正年間(1575〜1592年)に建立され、元禄7年に修復されている。
千本鳥居

神馬舎の近くから無数に建つ鳥居のトンネルがある。この千本鳥居からが奥の院への入口。
おもかる石

鳥居のトンネルを進むと一旦鳥居が途切れる場所がある。そこにあるのがおもかる石。灯篭の前で願い事を祈念して石を持ち上げ、想像していたよりも軽いと願いが叶い、重いと叶わないと言われる。
奥の院

おもかる石のある場所から先に進むと稲荷山の奥に入る。稲荷山を一回りするのに約2時間かかる。
根上り松

奥の院へ向かう千本鳥居の途中にある根上り松。根が上がるに通じることから、商売をする人や証券会社から篤く信仰されている。
また、人がひざまずいて祈る姿に似ていることから「膝松さん」とも呼ばれ、松の根元をくぐったり、木の肌を撫で身体の痛むところを撫でたりすると、腰や膝の痛みが治ると言い伝えられている。
大八嶋社

大八嶋大神を祀る大八嶋社(おおやしましゃ)。古来から社殿はなく、盤境をもって神鎮まります清浄の地とする。
山上の荒神峰に祀られていた地主神を現在地に鎮めたとも、荷田氏の祖神龍頭太に関わりのある場所とも伝えられている。
伏見稲荷大社の所在地
〒612-0882
京都市伏見区深草藪ノ内町68(地図)
伏見稲荷大社への行き方
JR稲荷駅から徒歩約1分
京阪伏見稲荷駅から徒歩約5分
伏見稲荷大社周辺の宿泊施設
スポンサード リンク
関連記事
- 伏見稲荷大社の稲荷造の本殿
- 伏見稲荷大社に千本鳥居が見られるようになったのは明治以降
- 伏見稲荷大社に新春のお参り・2024年
- 夕方に見る伏見稲荷大社の紅葉・2023年
- 伏見稲荷大社のおいなりさんライトアップで見る紅葉・2023年
- 秋の夕方に参拝した伏見稲荷大社・2023年
- 秋の夜に伏見稲荷大社をライトアップする千本灯籠。2023年
- 初秋の伏見稲荷大社は参拝者が増えつつある・2022年
- 京都市街を一望できる観光名所を集めました
- 伏見稲荷大社で見ごろが近づく桜・2022年
- 新春の伏見稲荷大社に参拝・2022年
- 豊臣秀吉が造営した伏見稲荷大社の楼門
- 伏見稲荷大社で茅の輪をくぐる・2021年
- 伏見稲荷大社にある後醍醐天皇御製が刻まれた石碑
- お山めぐりの終わりにくぐった間あき鳥居・2021年
- 伏見稲荷大社のお山めぐりで参拝した荒木神社と末廣大神・2021年
- 初午の日のお山めぐりで参拝した七福神と稲荷山に棲むネコ・2021年
- 初午の日にお山めぐり。間ノ峰と三ノ峰を通って稲荷山を下りる・2021年
- 伏見稲荷大社のお山めぐりで一ノ峰に到達・2021年
- 初午の日にお山めぐり。御膳谷奉拝所から長者社神蹟へ・2021年
- 伏見稲荷大社のお山めぐりで四ツ辻の田中社神蹟と眼力社に参拝・2021年
- 初午の日に伏見稲荷大社のお山めぐり-新池、三ツ辻・2021年
- 初午大祭の日に伏見稲荷大社に参拝・2021年
- 閑散とした梅雨の伏見稲荷大社・2020年
- 値上がり、腰や膝の痛み平癒を伏見稲荷大社の根上りの松に祈願
- 伏見稲荷大社の節分祭で行われた豆まき・2020年
- 12月に見る伏見稲荷大社の紅葉・2019年
- 伏見稲荷大社の石段脇に並ぶ末社
- 初秋に参拝した伏見稲荷大社・2019年
- 伏見稲荷大社の玉山稲荷社、白狐社、大八嶋社
- 荷田春満を祀る東丸神社は受験合格の神さま
- 梅雨明け前の伏見稲荷大社に参拝・2018年
- 伏見稲荷大社の満開の枝垂れ桜・2018年
- 冬でも賑わう伏見稲荷大社に参拝・2018年
- 伏見稲荷大社の松の下屋と御茶屋を拝観・京の冬の旅2018年
- 応仁の乱で活躍した足軽骨皮道賢が陣取った稲荷山
- 国際化が進む伏見稲荷大社
- 伏見稲荷大社の氏子は地元にいない
- 伏見稲荷大社でキツネと一緒に見る満開の桜・2016年
- 大混雑の伏見稲荷大社に元日に初詣・2016年
- 伏見稲荷大社の紅葉・2015年
- 本宮祭で賑わう伏見稲荷大社・2015年
- 合格祈願は東丸神社、商売繁盛祈願は伏見稲荷大社
- 元日に参拝者で賑わう伏見稲荷大社へ初詣・2015年
- 伏見稲荷大社の狐がくわえている物は4種類
- 伏見稲荷大社の紅葉・2013年
- 全国に2万社もある稲荷社
- 琵琶湖疎水沿いを散歩しながら伏見の桜名所を巡る
- 秋晴れの日に参拝した伏見稲荷大社
- 新年から伏見稲荷大社のお山めぐり
- 願い事がかなう鳥居と石・伏見稲荷大社
| 付近の主な観光名所 | ||
 光明院 |
 東福寺 |
 藤森神社 |