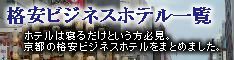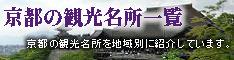金閣寺を紹介しています。
由緒、見どころ、所在地、最寄駅などの情報を掲載。
金閣寺(鹿苑寺)

由緒
金閣寺は、応永4年(1397年)に室町幕府3代将軍の足利義満が、西園寺家の山荘の北山第を譲り受けて造営した北山殿が始まり。
応永15年に義満が亡くなるとその遺言により4代将軍の義持が北山殿を禅寺に改め、義満の法号の鹿苑院殿に因み鹿苑寺(ろくおんじ)と名付けられた。開山は夢窓疎石。山号は北山(ほくざん)。臨済宗。相国寺の境外塔頭(たっちゅう)。
その後、応仁の乱(1467年)で金閣など一部の建物を残して焼失するが、豊臣家や徳川家の帰依を受けて徐々に復興されていった。
明治時代に入り、金閣の大修繕が行われる。
しかし、昭和25年(1950年)に放火によって金閣が焼失、同30年に再建された。
その後、昭和62年にも金閣の修理が行われている。
なお、金閣寺は平成6年(1994年)に世界文化遺産に登録されている。
金閣(舎利殿)

鏡湖池

池泉回遊式庭園の中心となる鏡湖池(きょうこち)。畠山石、赤松石、細川石など諸大名が競って献納した巨石が配されている。
陸舟の松

足利義満が自ら植えたと伝えられている陸舟(りくしゅう)の松。京都三松のひとつに数えられる。
龍門の瀧と鯉魚石

鯉が滝を登り龍となると言われる龍門の瀧。中央には、鯉魚石(りぎょせき)が置かれている。
安民沢と白蛇の塚

安民沢(あんみんたく)と呼ばれる池。右の石塔は白蛇の塚で、弁財天の使者とされる白蛇は西園寺家の守り神。
貴人榻

貴人が腰掛けた石とされる貴人榻(きじんとう)。
富士形手洗鉢

8代将軍の足利義政が愛用した手水鉢。
夕佳亭

江戸時代の茶人の金森宗和が好んだとされる茶席の夕佳亭(せっかてい)。
不動堂

本尊の石不動明王は弘法大師空海が彫ったもの。
金閣寺の所在地
〒603-8361
京都市北区金閣寺町1(地図)
金閣寺への行き方
京福北野白梅町駅から徒歩約21分
市バス「金閣寺前」から徒歩約1分
※拝観料500円が必要。
金閣寺周辺の宿泊施設
京福北野白梅町駅周辺のホテル一覧
京福北野白梅町駅周辺の旅館一覧
スポンサード リンク
関連記事
| 付近の主な観光名所 | ||
 源光庵 |
 常照寺 |
 光悦寺 |
 龍安寺 |
 等持院 |
 仁和寺 |