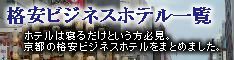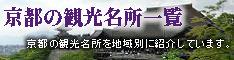高山寺を紹介しています。
由緒、見どころ、所在地、最寄駅などの情報を掲載。
高山寺

由緒
高山寺は、宝亀5年(774年)に光仁天皇の勅願によって創建された新願寺都賀尾坊(とがのおぼう)が始まり。山号は栂尾山(とがのおさん)。真言宗の単立寺院。
弘仁5年(814年)に栂尾十無尽院(とがのおじゅうむじんいん)と改称される。
その後、荒廃するが、文覚(もんがく)が神護寺を再建した際に神護寺の別院となった。しかし、文覚が失脚したことで再び寺域は荒廃する。
中興したのは、文覚の弟子・明恵(みょうえ)で建永元年(1206年)に後鳥羽上皇の院宣によって華厳宗の道場を開設した。その時に後鳥羽上皇から「日出先照高山之寺」の勅額を賜り、高山寺と改称した。
しかし、天文16年(1547年)に兵火によって石水院を残し焼失する。
その後、寛永11年(1643年)に仁和寺から古御堂を移して金堂とし、同13年に永弁、秀融が諸堂の再建を行い旧観をやや取り戻した。
明治維新で再び衰退するが、昭和6年(1931年)に明恵上人七百年後遠忌記念として茶室遺香庵が建てられ、同34年には国宝や重要文化財の永久保存のため収蔵庫が建設された。また、昭和36年に開山堂の横に聖観世音菩薩像が安置された。その後、昭和56年に春日神社が金堂の横に復興されている。
なお、高山寺は平成6年(1994年)に世界文化遺産に登録されている。
表参道の入口

高山寺の表参道側の入口。裏参道からも境内に入ることができる。
金堂

寛永11年に仁和寺から移された金堂。表参道の入口からまっすぐ金堂道を上がっていくと着く。
明恵上人御廟

金堂から東に旧石水院跡を超えた場所にある明恵上人御廟。明恵上人は高山時中興の祖で華厳、真言、律、禅などの奥儀を体得したとされる。
仏足石

旧石水院跡と明恵上人御廟の間にある仏足石。石の上に大きな足形がある。
開山堂

明恵上人が晩年に過ごした草庵跡とされる。明恵上人坐像が安置されている。
石水院

鎌倉時代唯一の遺構。国宝に指定されている。金堂の東にあったものを明治22年(1889年)に現在地に移転した。明恵上人樹上坐禅図や鳥獣人物戯画(複本)などが保存されている。
日本最古の茶園

境内の中央に位置する日本最古の茶園。宋から茶を持ち帰った栄西から明恵上人に茶の種が贈られた。高山寺のある栂尾山が茶の発祥地とされる。
遺香庵

明恵上人七百年遠忌にあたる昭和6年(1931年)に大久保利武が企画し、高橋箒庵が総代となって寄進された茶室。
設計は高橋箒庵、建築は3代目木村清兵衛、露地作庭は7代目小川治兵衛が手掛けた。
裏参道

高山寺の裏参道。バスの停留所に近く、ここから入山するのが便利。
高山寺の所在地
〒616-8295
京都市右京区梅ヶ畑栂尾8(地図)
高山寺への行き方
JRバスまたは市バスの「栂ノ尾」から徒歩約3分
※石水院は拝観料1,000円が必要。紅葉の時期は別途入山料500円が必要。
高山寺周辺の宿泊施設
スポンサード リンク
関連記事
| 付近の主な観光名所 | ||
 神護寺 |
 西明寺 |
 平岡八幡宮 |