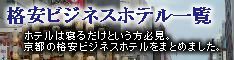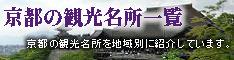随心院を紹介しています。
由緒、見どころ、所在地、最寄駅などの情報を掲載。
随心院

由緒
随心院は、正暦2年(991年)に仁海が創建した牛皮山曼荼羅寺(ぎゅうひざんまんだらじ)が始まり。山号は牛皮山(ぎゅうひざん)。真言宗善通寺派。
寺名の由来は以下の通り。
ある日、牛に生まれ変わった亡き母が仁海の夢に現れた。仁海は、その牛を探しだし世話をしていたが、間もなく死んだため、悲しんで牛の皮に両界曼荼羅の尊像を描き本尊にした。
その後、第5世の増俊が曼荼羅寺の子院として随心院を建立。
寛喜元年(1229年)に第7世のの親厳が、後堀河天皇より門跡の宣旨を賜り、以来、随心院門跡と称するようになった。
承久の乱(1221年)、応仁の乱(1467年)で多くの伽藍が焼失したが、慶長4年(1599年)に本堂が再建され、その後も九条家、二条家の寄進により再興された。
明治41年(1908年)に独立し真言宗小野派となるが、昭和6年(1931年)に善通寺派に所属した。
薬医門

寛永年間(1624〜1644年)に徳川秀忠の娘である天真院尼の寄進で建てられた薬医門。
庫裡

宝暦3年(1753年)に二条家から移築された庫裡(くり)。
小野小町歌碑

庫裡近くに置かれた小野小町歌碑。
花のいろは うつりにけりな いたづらに わが身よにふる ながめせしまに
随心院は小野小町が生まれた地と伝えられており、建物内には、小野小町の晩年の姿を写した卒塔婆小町坐像や小町作と伝わる文張地蔵尊像などが安置されている。
本堂

慶長4年に再建された寝殿造りの本堂。定朝(じょうちょう)作の阿弥陀如来坐像など多くの重要文化財が安置されている。
小野小町化粧の井戸

小野小町が使用したと伝えられている化粧の井戸。
仁海僧正供養塔

牛皮曼荼羅寺を創建した仁海の供養塔。
小町榧

仁海僧正供養塔の後ろに植えられている小町榧(かや)。深草少将の百夜通(ももよかよい)に登場する榧の実を小町がまいたとされる。
文塚

小野小町に寄せられた千束の恋文を埋めた塚と伝えられている文塚。
小野梅園

毎年3月に特別公開される小野梅園。遅咲き、うす紅色の「はねずの梅」が多数植えられている。
随心院の所在地
〒607-8257
京都市山科区小野御霊町35(地図)
随心院への行き方
地下鉄小野駅から徒歩約8分
※建物内は拝観料500円が必要。
※小野梅園は拝観料500円が必要。
スポンサード リンク
関連記事
| 付近の主な観光名所 | ||
 勧修寺 |
 醍醐寺 |
 毘沙門堂 |